コラム:振袖って何年もつの?


洋服は、トレンドの移り変わりが本当に激しいので、母から子へ、ということがあまりないですよね。
振袖は柄の流行こそあれど、洋服のように形が変わったりしませんので、流行おくれというのが無いものになります。
なので、振袖を母から子へ、子から孫へ、孫からひ孫へ・・・と受け継ぐことができますが、いったい振袖って何年持つのか?ふと気になった事ありませんか?
今回は、振袖がどこまで着れるのか・・・?ということを深堀していきたいと思います
まず、ご覧いただきたいのが正倉院のお着物になります。

引用はこちらのサイトから。
もうボロボロになっておりますね。
正倉院は西暦756年に建てられたものですから、単純計算すると・・・約1270年前になります(-_-)zzz
このブログにも書いてある通り、これが陶磁器などであれば、永久に残り続ける工芸品になり得たはずです。
しかしながら、陶磁器は無機物、着物は有機物である絹からできております。
従って、だんだん劣化していくことは避けられない繊維ではありますね。悲しい・・・。
絹糸の寿命について
一般的に絹糸の寿命は100年と言われています。
ただし、これはあくまで「業界的」な話になります。
絹糸の科学論文を探しましたが、全くみつかりませんでした\(^o^)/
科学的裏付けを手に入れたうえで面白おかしくご紹介したかったのですが・・・(;_:)
日光の強さ、湿度の強さで、どの程度絹はダメージを受けるのか?という論文を知っているかた、是非教えてください!
親子何代まで持つ?
さて、お振袖は何年もつのか・・・?というお話になってきます。
先程も申しましたように、「業界的」な標準は100年と言われております。
じゃあ単純に親子3代までなのか?
もちろんそんなことはありません。
インターネット検索のブログで確認できるものとしては、ひいばあちゃんからの振袖や、曾祖母様からの振袖など
4代目になっても着ているお写真などを散見されます。
保管状態によっては、とても長く着ることができる、それがお着物なのです。
洋服には絶対に持つことのできない特徴ですね。
なぜ長く着る事ができるのか
お洋服の柄やデザインは、流行り廃りがあります。その時の流行というのはほぼ1年おきに変わってしまいます。
しかしながら、お着物は「民族衣装」という日本人の伝統的な服装になります。
昔から使っていた柄や、お着物の形もほぼ変わらずに現代まで受け継がれています。
昔から着られている衣裳に昔の柄をいれたとしても、なんの違和感もありません。
また、昔の柄といっても、工夫次第で可愛らしいデザインに変貌することもあります。
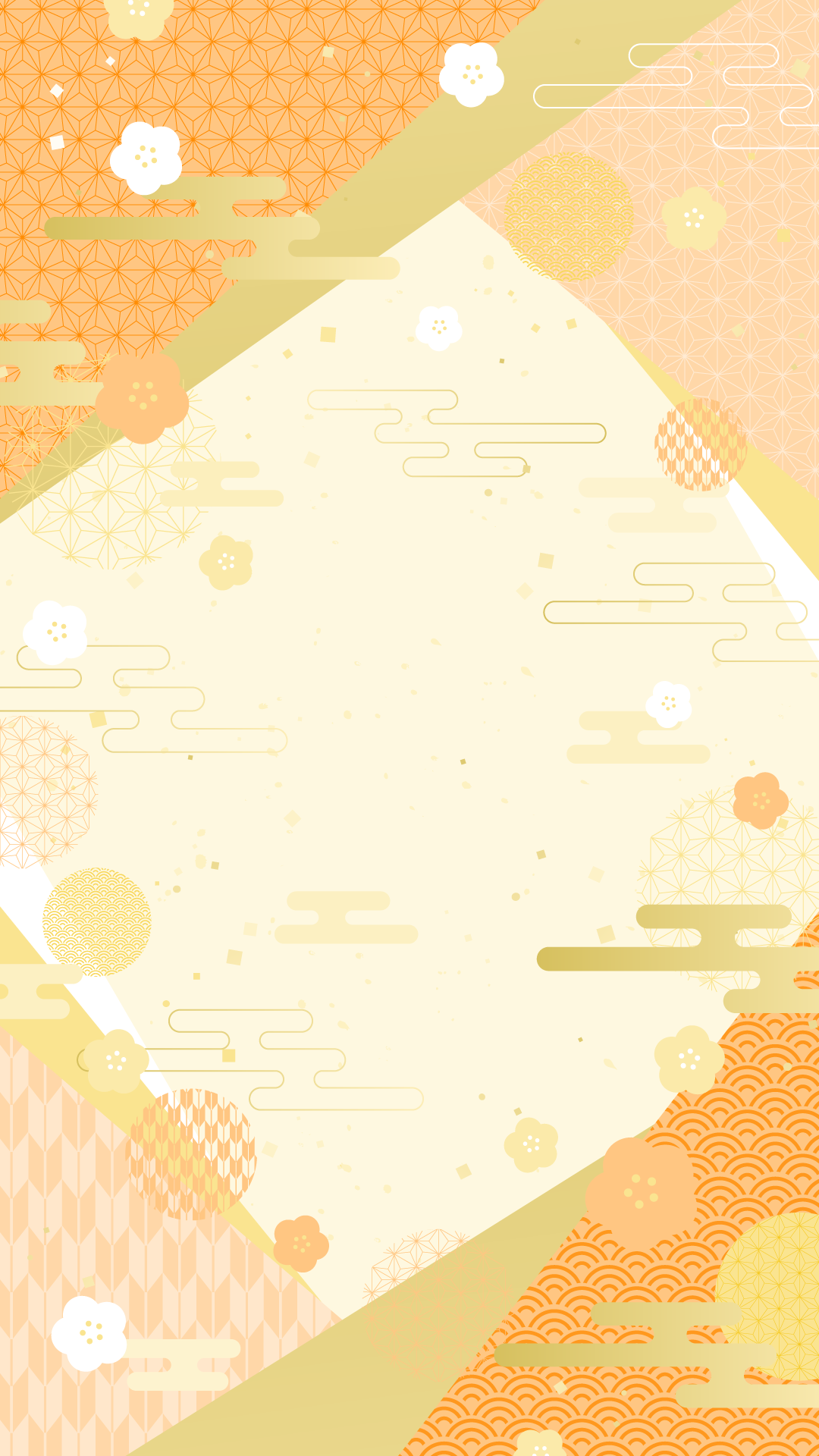
まとめ
本当は科学的な裏付けから、面白おかしく「へぇー(゜o゜)」というような記事を書きたかったのですが
まったくそのような実験結果を検索から拾う事ができませんでした(^_^;)
とはいえ、お着物の保管状態によっては
親子4代まで着れることがわかりました。
曾祖母→祖母→母→自分
なにか、歴史的なロマンを感じませんか?歴史を受け継ぐって、本当に素敵なことだと私は感じております。
八百万の神ではありませんが
もしかしたら、大切に受け継がれたお着物には、神様の依り代になっているかもしれませんね。
– * – * – * – * – * – * – * – *– * – * – * – * – * – * – * – *– * – * – * – * – * – * – * – *
〒631-0821
奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー1F

皆様の特別な日を彩る振袖の専門店です
豊富なデザインとサイズを取り揃え、初心者の方でも安心してお選びいただけるサポート体制が整っています。
プロのスタッフが一人ひとりに寄り添い、最適な振袖を提案いたしますので、心に残る素敵な一着が見つかること間違いなしです!
↑振袖無料相談会・撮影プランでご予約の方はこちらのリンクから↑
※返信には2日~3日ほどお時間をいただく場合があるので急ぎの方、当日予約は電話予約をお願いします。
※迷惑メール設定のあるアドレスにはお店からの返信が届かない可能性があります。
– * – * – * – * – * – * – * – *– * – * – * – * – * – * – * – *– * – * – * – * – * – * – * – *


